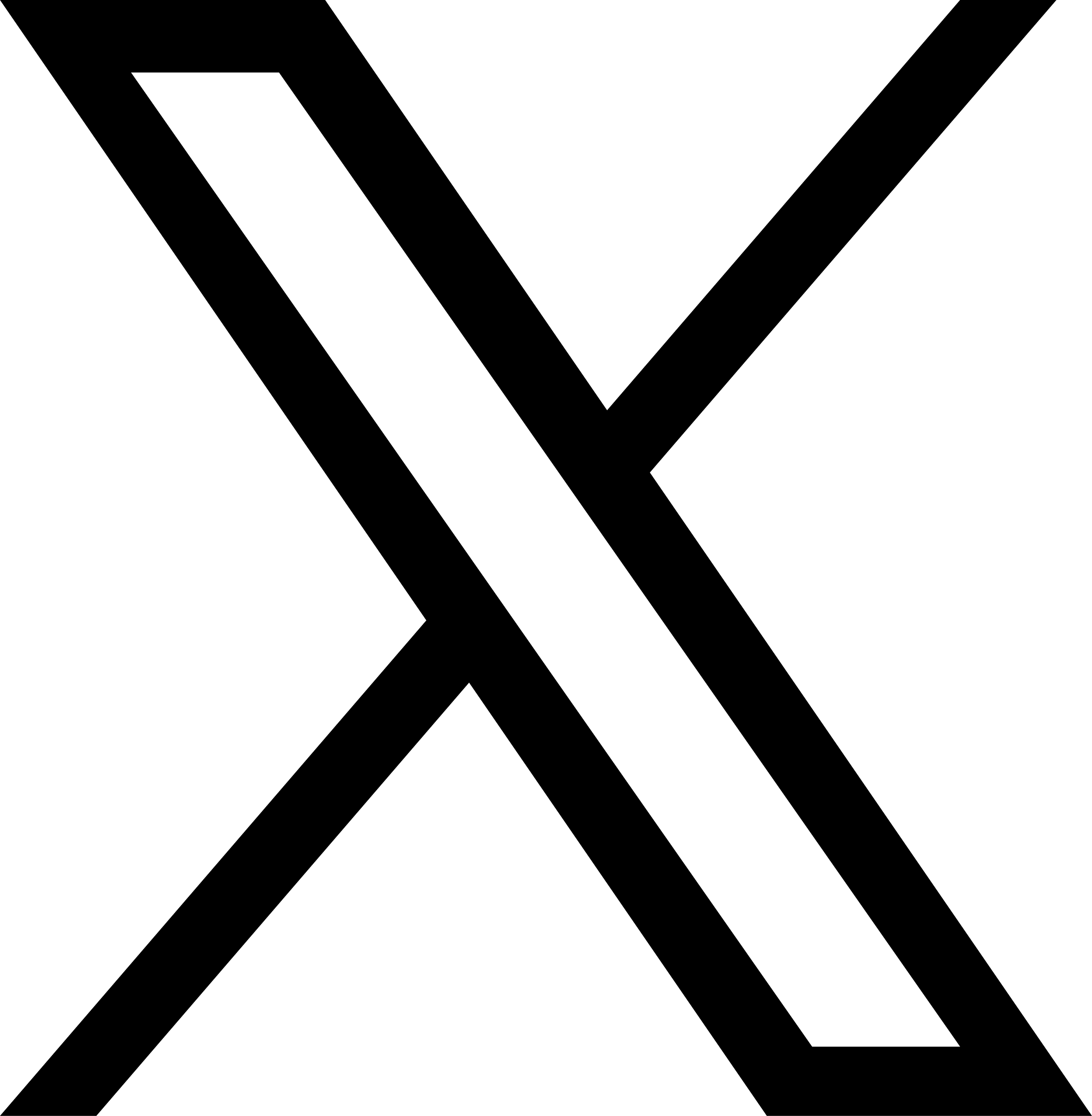オフィスや事務所の床掃除のポイントとは|汚れの原因とおすすめの掃除道具
2022.10.12
業界コラム

毎日快適に働くためにも、オフィス・事務所を清潔な状態に保つのは非常に重要です。
汚れは時間が経つにつれ、落としづらい頑固な汚れへと変化していきます。そのため、毎日こまめに掃除しなければなりません。しかし、毎日の掃除は意外と手間や時間を使うものです。掃除コストをできるだけ軽減し、効果的に掃除するには、汚れの特徴について理解しておく必要があります。
本項では、オフィスや事務所の床材や汚れの種類による清掃のポイントをご紹介します。
オフィス掃除を行う頻度の目安は?
毎日しっかりとオフィスを隅々まで掃除するのは、とても骨の折れる作業です。
掃除を効率化し、清潔なオフィスを維持するには、「日常掃除」と「定期清掃」の2つの観点からアプローチするのが効果的です。
日常掃除とは、文字通り日常的に行う掃除のことです。オフィスを隅々までしっかり掃除するのではなく、使用頻度が高い場所を中心に、目につきやすい場所を清潔な状態に維持するために行います。
具体的にはデスク周辺やドア周辺、共有スペースのテーブルの上などのこまめな掃除、フロアの掃除機がけ、ごみ捨てなどです。雑巾や掃除機、ほうきとちりとりなどを使った、比較的負担の小さな清掃作業が主です。
一方の定期清掃では、日常清掃で落とし切れない頑固な汚れを掃除したり、普段はあまり目につかない場所や使用頻度の低い場所を掃除したりします。
頻度としては数ヶ月に1回から年に1回程度で行われるのが一般的で、床のワックスがけや窓の拭き掃除、エアコンのフィルター掃除など、比較的手間と時間のかかる作業が主です。
会社によっては高圧洗浄機を使って丸一日を費やすこともあれば、清掃業者に委託するケースもあります。
日ごろから日常清掃を心掛け、たまに定期清掃でオフィスをしっかりメンテナンスすることで、最小限のコストで清潔なオフィスを維持しやすくなります。
オフィスを掃除しないと起こる弊害
オフィスを掃除しないことで起こり得る一番の弊害は、スタッフのパフォーマンスを低下させる可能性があることです。
オフィスが汚いと、スタッフの仕事に対するモチベーションに悪影響を与える可能性があります。「一事が万事」ではありませんが、不衛生で整理整頓されていないオフィス環境を許容することで、業務内容もずさんになり、結果としてスタッフの「仕事に対するやりがい」や「仕事の価値」などエンゲージメントを低下させる原因になります。
スタッフには、会社や組織に対する「所属意識」があります。所属先が立派だと、スタッフもその自覚をもって組織の価値に見合った意識を持ちます。しかし、オフィス環境の整備やスタッフのケアをないがしろにする組織に対し、スタッフは健全な所属意識を養うことができません。
清潔なオフィス環境の維持は、実は業務成績にダイレクトに影響する重要な項目なのです。
また、オフィスが汚れていると、来客に与える印象も悪くなります。特にエントランスや応接室は、いわば会社の顔のようなもの。会社の格が問われる重要な空間です。いずれにせよ、オフィスや事務所を清潔に保つのは、業績を伸ばすためにもスタッフの士気を高めるためにも必須といえるでしょう。
【場所別】オフィスの掃除方法

オフィス内には、さまざまな備品や設備、区画があります。効率的に掃除し、手間と時間を短縮しながら最大限の効果を発揮するためには、それぞれの場所に合った適切な方法を選ぶ必要があります。
ここでは、オフィス内のそれぞれの場所に合う掃除方法について詳しく解説します。
デスク周辺
デスク周辺は、各自が日常清掃でこまめに掃除するのが理想的です。
たとえば書類の整理整頓をはじめ、デスクにこぼしてしまった飲食物の汚れや、皮脂などの汚れなどは、ウェットシートやアルコールスプレーなどを用いて、こまめに掃除する習慣をつけましょう。
マウスの汚れやモニターの縁の汚れなど、パソコン周りの掃除には、掃除用ブラシやエアダスターの使用がおすすめです。掃除がしにくいキーボードには、粘着性のスライムなどが便利です。
オフィス家具
日常業務で使用するオフィスチェアや、共有スペースのテーブル・ソファなどは、汗や皮脂汚れなどが付着しやすいため、定期的に掃除したいところです。
チェアやソファの掃除方法は形状や素材により異なりますが、布製やメッシュ製のものは、薄めた住居用洗剤や重曹水を含ませて硬く絞ったタオルや雑巾で、優しく拭き掃除をするのが適切です。力を入れると形状が歪んだり、素材を傷めたりする可能性があるのでご注意ください。
汚れが落ちたら、乾いたタオルや雑巾などで空拭きをして仕上げましょう。
合成皮革やビニール素材は、水拭き掃除で十分です。汚れが落ちにくい場合は、住居用洗剤を含ませて絞った雑巾などで汚れを落とし、空拭きで仕上げましょう。
本革製の革張りタイプのオフィス家具は、洗剤を使用したり過剰な水分を与えたりすると、変形や変色の原因になります。革専用のクリーナーを使って掃除しましょう。
床
床掃除は、オフィス掃除の中でももっとも時間と労力を要するため、できるだけ効率的に掃除したいところです。
フローリングの場合は、フロアモップや掃除機を使って掃除しましょう。床材にこびりついた花粉や汚れは、掃除機ではなかなか除去できません。そのためフロアモップやコロコロなどを使用した定期的な掃除が必要です。
日常掃除は掃除機でチリやホコリを除去し、定期掃除で拭き掃除をするルーティンを組むのが理想的ですが、可能であれば、たとえ簡易的ではあっても日ごろからフロアモップやコロコロで掃除するようにしましょう。
丁寧な日常掃除ができれば、オフィス環境をいっそう快適に維持できますし、定期掃除のコストも軽減されます。
また、床掃除の手間を軽減するために、床掃除に特化した便利なアイテムを選ぶことも重要です。
オフィス・事務所で使われる4つの床材
床掃除を行う際には、汚れの種類ごとに適切な掃除方法を選択しなければいけません。また、床の種類や特徴によって、発生しやすい汚れの種類も異なります。
つまり、効果的に床掃除を行うためには、オフィスで使用されている床材の特徴を最初に理解しておく必要があります。
ここでは、オフィスや事務所で用いられる床の種類をご紹介します。自社でどういった床材が使用されているのか、改めて確認してみましょう。
防滑床(防滑性ビニル床シート)
防滑床(防滑性ビニル床シート)とは、その名の通り滑りにくい素材が用いられた床素材です。たとえ靴や床が濡れていたとしても、床が防滑床であれば滑って転倒するリスクを軽減できます。
「濡れていても滑りにくい」という特徴から、厨房や飲食店、プールといった水が頻繁に用いられる場所で導入されることが多い素材です。
また、一般的なオフィス・事務所であっても、階段周辺に導入すると雨の日でも安心して働くことができます。雨の日に床が濡れていることが原因で発生する転倒事故は毎年発生しており、時には死亡事故につながることも。
そのため、防滑床は労働災害を予防する意図で導入されることも多い素材です。
タイルカーペット
タイルカーペットとは、1辺およそ40~50cm四方のパネル型をしたカーペットです。
一般家庭で用いられるタイルカーペットは、裏面が塩化ビニルやフェルトなどの素材が一般的です。一方、オフィス・事務所用のタイルカーペットは、接着剤を用いて直接床に貼り付けられるケースが多く、取り外しも容易な仕様となっています。
オフィスの形状や配線に沿って細かく形を調整できるため、多くのオフィス・事務所で採用されています。静電気や汚れの防止機能や、耐久性が高いのも特徴です。カラーやデザインも豊富で、設置する場所や企業の雰囲気、ブランディングに合わせた製品を選定できます。
大理石・フローリングなどの天然素材
大理石や木質系フローリングなどの天然素材も、オフィス・事務所の床材として使用されています。光沢感と模様が特徴的な大理石は、他の床素材に比べて高級感に秀でています。
フローリングは、高級感という面では大理石に劣るものの、清潔感と温かみを演出しやすいのが特徴です。これら床素材は天然素材特有の細かな凹凸を持っており、小さなほこりやちょっとした汚れが目立ちにくいのがメリットです。
一方で、細かな凹凸にほこりや汚れが蓄積されていくと、シミや黒ずみへと変化し、簡単には落とせなくなってしまうデメリットもあります。清潔な状態を保つためにも、日ごろの掃除が欠かせない床素材といえるでしょう。
ビニルタイプ
タイルカーペット同様、ポリ塩化ビニル素材のタイルやシートも、オフィス・事務所用床材としてしばしば用いられます。
耐久性やクッション性に優れており、製品によっては耐薬性や耐電性能を有しているものもあります。
また、木目調のフローリング柄や模様が美しいストーン柄など、デザインやカラーも豊富です。そのため、企業独自のニーズに沿った製品を採用しやすいといったメリットがあります。
オフィス・事務所の床が汚れる原因とデメリット

ここでは、オフィス・事務所の床にどのような汚れが発生するのかを確認していきましょう。それぞれの汚れ別に有効な清掃方法も紹介するので、清掃の参考にしてください。
オフィス・事務所の3つの汚れの種類と原因
オフィス・事務所の床に発生する汚れには大きく3つの種類があり、それぞれ発生する原因が異なります。
汚れを放置してしまうと、見た目の印象が悪くなるだけでなく、人体へも悪影響を及ぼす恐れもあります。それぞれの違いを把握した上で、適切な対応を行いましょう。
・黄ばみ
床に付着した水滴を放置してしまうと、床に使用されている素材と反応を起こし、黄色く変色する恐れがあります。
水の付着による黄ばみは、塩化ビニル樹脂が用いられた床で発生しやすいといわれています。
ビニルタイプのタイルやシートを、オフィス・事務所の床に採用している場合は、黄ばみ汚れが発生する恐れがあるため注意しましょう。
また、椅子やテーブルといった備品に滑り止めのゴムが装着されている場合、黄ばみ汚れの原因になる可能性があります。これらのゴムは長時間放置されることで黄色く変色していき、接触している床にも影響を与えるのです。この現象は「ゴム汚染」と呼ばれています。
一度ゴム汚染によって床に黄ばみが発生すると、簡単には除去できない頑固な汚れとなってしまうため注意が必要です。
・黒ずみ
濡れた床を放置してしまうと、黄ばみだけでなく黒ずみ汚れにもつながります。黒ずみの原因はカビです。長時間放置すると床材の深部にまで浸透する可能性があります。
内部までカビが浸透してしまうと、清掃業者でも黒ずみを除去できなくなってしまうため、事前の対策が必要です。
また、床材に使用されているワックスの劣化によっても、黒ずみ汚れが発生する場合があります。定期的に床掃除をしたからといって防げるわけではないところが厄介です。
中には、黒ずみ汚れが発生した上から、新たにワックスを塗布して誤魔化しているケースもあるため、床材にワックスが用いられている場合は注意しましょう。
・油汚れ
床に付着した油汚れを放置してしまうと、黒ずみ汚れへとつながる恐れがあります。
油汚れというと、厨房やキッチンで発生するものであり、オフィス・事務所には関係ないと感じる方もいるかもしれません。しかし、実際には従業員が勤務場所で食事をとる際、揚げ物を食べこぼしたり、カップ麺をすすることでスープが飛び散ったりすることで、油汚れが徐々に蓄積されていきます。こうした油汚れが放置されると、やがて黒ずみへと変化していくのです。
汚れの種類別の落とし方
次に、オフィス・事務所で発生する3種類の汚れの落とし方について説明します。
これらの汚れは、放置した時間が長ければ長いほど頑固な汚れとなり、対応も難しくなってしまいます。
そのため、ここでは事前に行うべき対応も併せて紹介します。
・床の黄ばみの落とし方
ビニルタイプの床に発生した黄ばみ汚れは、基本的に中性洗剤を活用すれば除去できます。掃除方法も簡単で、以下の手順で行えば黄ばみ汚れを落とせます。
1.ほうきや掃除機で目に見えるごみを取り除く
2.固く絞った雑巾で水拭きをする
3.雑巾に中性洗剤を数滴たらして泡立てる
4.その後、黄ばみ部分を拭く
5.最後に別の雑巾で水拭きをした後、乾拭きで水気を取る
もし、この方法で取り除けないほど頑固な黄ばみ汚れとなっていた場合、中性洗剤の代わりにアルカリ性洗剤を試してみましょう。
ただし、アルカリ性洗剤は刺激が強いため、濃度に合わせて水に溶かしてから使用したり、肌が弱い人は触らないようにしたりなどの工夫が必要です。
一方、ゴム汚染によって発生した黄ばみ汚れは、基本的に落とすことができません。仮に、黄ばみ汚れができたばかりで表層部にとどまっている場合であれば、メラミンスポンジで落とせる可能性があります。
しかし、床表面を傷つける恐れがあるため、あまりおすすめできません。そのため、ゴム汚染による黄ばみは事前の対策によって対応するのが適切です。たとえば、滑り止めゴムと床の間にシリコンシートや紙などを挟むのも良いでしょう。
・床の黒ずみの落とし方
カビによる黒ずみ汚れには、アルコールスプレーがおすすめです。アルコールにはカビの繁殖を防ぐ効果があるため、掃除に使用することで黒ずみ汚れの除去にも活用できます。
手順は次の通りです。
1.黒ずみ汚れにアルコールスプレーを吹き付ける
2.アルコールスプレーの水気が無くなってきたら、中性洗剤を含んだ濡れ雑巾で拭く
3.別の濡れ雑巾で水拭きし、洗剤を落とす
4.最後に乾拭きを行い、水気を取る
カビが発生してから時間が経っておらず、表層部にとどまっているのであれば、上記の掃除方法で黒ずみ汚れを落とせるでしょう。
ただし、黒ずみ汚れになってから時間が経ち、カビが奥深くまで浸透してしまっている場合は、簡単に除去するのは難しいため、専門の業者に相談するのがおすすめです。
ワックスの劣化による黒ずみ汚れに関しては、一度ワックスを剥離するのも選択肢に入れましょう。なぜなら、黒ずみ汚れが発生した上から新しいワックスが塗布されていた場合、まずはワックスそのものを剥離しなければ黒ずみ汚れを落とせないためです。
ワックスの剥離も専門的な溶剤や機械を必要とするため、専門の業者に依頼するのが良いでしょう。
・油汚れの落とし方
食べ物による簡単な油汚れは、中性洗剤を用いれば簡単に落とせます。
手順は次の通りです。
1.中性洗剤を水に溶かす
2.この溶液を雑巾に染み込ませ、油汚れをふき取る
3.別の雑巾で水拭きをした後、乾拭きで水気を取り除く
注意点として、油汚れそのものに気づきにくい点があげられます。
また、油が透明なため汚れている場所が明確に分からず、気づいた時には黒ずみ汚れになっていた──ということもあるでしょう。
黒ずみ汚れも、放置していると頑固な汚れになってしまいます。
オフィス・事務所での油汚れを対策するのであれば、食事場所の制限を検討するのも良いでしょう。食事場所が指定されているのであれば、その場所では普段から油汚れを考慮した清掃を行えば良いため、清掃効率が高まります。
オフィス・事務所の日常清掃のおすすめ用具

最後に、オフィス・事務所の日常清掃におすすめの掃除用具をご紹介します。
一般的な道具との比較も交えながらご紹介するので、効率的に掃除をしたい方や掃除用具の新調を考えている方はぜひ参考にしてください。
フロアモップ:FXスベールラーグ
FXスベールラーグは、防滑床専用のフロアモップです。
防滑床は水に濡れても滑りにくいというメリットがあるものの、凸凹があるため掃除がしづらく、凹んでいる部分には汚れがたまりやすいのが難点です。
凹み部分に汚れや水気がたまってしまうと、黒ずみ汚れの原因にもなります。
防滑床用FXスベールラーグは、ヘッド部分が極細繊維となっており、細かい凹凸があってもしっかりと汚れを除去します。
掃除範囲の広い日常清掃であれば、一つの清掃箇所にかけられる時間も限られているため、専用の掃除道具を用いて効率を高めるのがおすすめです。

※商品ページ:防滑床用FXスベールラーグ 45cm グレー
雑巾・クロス:FX制菌クロスTIOTIO
FX制菌クロスTioTioは独自のTioTio加工が施されている、制菌性と抗菌防臭に優れた清掃用クロスです。
清掃用クロスはさまざまな場所を掃除するのに使用された後、固く絞って自然乾燥させるのが一般的ですが、この使用方法では、汚れと水気のあるクロスに雑菌が繁殖してしまう恐れがあります。
さらに、雑菌が繁殖したクロスは独特の異臭を放つだけでなく、清掃に使用するとかえって雑菌を広げてしまうリスクもあるのです。
FX制菌クロスTioTioであれば、使用した後も抗菌作用によって雑菌の繁殖を防ぐことができます。また、速乾性能にも優れているため、日々の手入れが簡単なのもおすすめポイントです。

※商品ページ:FX制菌クロスTioTio
粘着クリーナー:オフィスコロコロ フロアクリンスペア
オフィスコロコロ フロアクリンスペアは、通常の粘着ローラーよりも吸着力が高いのが特徴です。
通常の粘着ローラーでも、一般的な家庭で使用する分には問題ないかもしれません。しかし、多くの人が出入りするオフィス・事務所では、通常の粘着ローラーでは対応しきれないケースが大半でしょう。
特にオフィス・事務所の床がタイルカーペットだった場合、繊維の間に入り込んだほこりを取り除くのは困難です。
オフィスコロコロ フロアクリンスペアであれば、多くのゴミやホコリが詰まったタイルカーペットでも問題なくきれいに仕上げることが可能です。
タイルカーペットが使用されている床には、特におすすめの製品です。

※商品ページ:オフィスコロコロ フロアクリンスペア3巻入160mm C4352
汚れごとの特徴を把握して効果的に掃除をしよう
床に付着する汚れには「黄ばみ汚れ」「黒ずみ汚れ」「油汚れ」の3種類があり、それぞれ原因や事前の対策が異なります。
また、使用されている床材によって、適切な掃除方法も違います。
今回ご紹介した床材の種類や汚れ別の清掃方法を参考に、毎日利用するオフィス・事務所を清潔に保ちましょう。
関連コラム
-

-
業務用掃除機は家庭用と何が違うの?
正しい選び方とおすすめ掃除機を紹介掃除機における業務用と家庭用の違いは、主に吸引力と耐久性、容量の3つにあります。本記事では、オフィスや工場、ホテルなど、現場に合った業務用掃除機の選び方を徹底解説。種類や用途、注意点も分かり、貴社にぴったりのおすすめの掃除機が見つかります。
-

-
失敗しない業務用ゴミ箱の選び方
|知っておくべきポイントとおすすめ商品店舗やオフィスに最適な業務用ゴミ箱の選び方を解説。容量・素材・機能といった基本のポイントから、設置場所ごとの選び方まで分かりやすく紹介。テラモトの「ニートシリーズ」など、おすすめ商品も多数掲載しています。
-

-
業務用テントの正しい選び方!
現場担当者が知っておくべき5つのポイントとおすすめ商品業務用テントの失敗しない選び方を5つのポイントで解説。形状・サイズ・素材選択からメンテナンス方法まで、専門知識不要で適切な商品選びができる実践ガイドです。安全で効率的な業務環境実現のための、実践的な選択方法をご紹介します。
-

-
二酸化炭素中毒を防ぐために│CO2濃度の基準値と対策を徹底解説